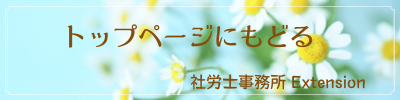若手のAさんは地方への出張が頻繁にある。でも、なんだか憂鬱そう。声をかけて聞いてみると、職場にお土産を買って帰るのが負担なんだそう。お土産がないと「Aさんがいない間代わりに仕事していたのに、何にもナシ?!」と言われるそうで・・・。「こんなことならもう出張に行きたくない」とAさん。困ったなあ、会社としてどうするべき?
**
職場でのお土産問題に頭を悩ませる人事担当者さんです。プライベートの旅行で、会社を休んでいる間のフォローに感謝を込めてお土産を配る・・・ということが習慣になっている職場もあるかもしれません。
とはいえ、出張は会社の業務のために行われるもの。職場へのお土産購入がネックとなって、出張する社員のモチベーションが低下するのでは、人材マネジメント上問題があります。
そこで今回は、出張に伴う職場へのお土産購入問題に会社はどう対応するべきなのか、詳しく確認していきたいと思います。
出張旅費について

「出張する人には出張旅費が会社から出るのだから、職場へのお土産ぐらいいいのでは?」という考え方もあるでしょう。そこでまず、会社が支給する出張旅費について整理したいと思います。
出張旅費は、社員が職務遂行のため旅行した場合にその費用を弁償しようとするものです。出張旅費の支給方式は、「証拠方式」と「定額方式」の2パターンに大別することができます。
前者の「証拠方式」とは、出張者が提出する証拠書類(領収書など)に基づいて支給額を定めるものです。実費弁償という旅費の原則に沿っていますが、証拠書類の確保が難しいこともあります(券売機で切符を買うと領収書が出ないなど)。また本当に業務のために必要とされた費用であるかの判定が難しい点もあり、出張者や手続き担当者の事務負担が増えがちです。
後者の「定額方式」は、個々の旅費種目(鉄道賃、日当、宿泊料など)について標準的な実費額をもとに計算した定額を支給するものです。手続きが簡単なので、事務的なコストを下げることができます。ただし、標準額を決めることが難しく、実費が標準額と大幅な差がある場合(標準額が急な物価高に追いついていないなど)は、調整が必要となります。
出張にあたって日当が支給されるとはいえ、お土産代は日当を超える金額になることも多く、「お土産の習慣をなんとかしてほしい・・・」というのが出張回数の多い社員のホンネかもしれません。
実務的にどうする?

特に国内出張の場合、若手社員であってもたびたび遠方へ出張に赴く機会も多いようです。「給料もまだ低いのにお土産代がイタイ・・・」という声も少なくないでしょう。中堅社員にしても、住宅ローンや子どもの教育費がかさむ世代であり、お土産代が懐事情に与える影響も小さくはないでしょう。
出張先でお店が見当たらないと、手ごろなお土産を探し回るために、現地の仕事を早めに切り上げる・・・というようなことがあれば、何のための出張なのかわかりません。また、冒頭の例のようにお土産の購入が負担になって、出張業務に対するモチベーションが低下してしまうのでは本末転倒です。
会社は、出張のための旅行を命令したからには、所要の出張旅費を支給して社員に職務遂行に支障が出ないようにしなければなりませんが、職場のコミュニケーションのためとはいえ、お土産購入の費用までカバーすべきなのか疑問があります。
そこで会社としては、人事総務部門が中心となって、現代となってはそぐわない職場のしきたりを見直す必要があるでしょう。出張に伴う職場へのお土産購入を禁止とするルールを設定するのは、ひとつの方法です。出張者によってお土産を購入する人、購入しない人がいてはなかなか「悪しき慣習」は是正されないことが考えられます。
**
出張に伴う職場へのお土産購入を禁止とするルールを設けると、「プライベートの旅行では職場へのお土産を買ってもよくて、出張の場合はダメなの?」と誤解する人もいるかもしれません。
プライベートの旅行でも出張でも職場へのお土産購入はNG、と全面禁止にするのも考え方のひとつです。職場へのお土産をきっかけに会話が弾むのはもちろんいいことですが、そのこと自体が負担になっては意味がありませんものね。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事