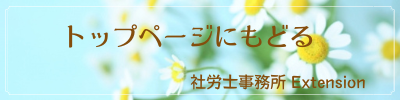「自社の社員を取引先に出向させて業務を行い、それを会社の売上げとして計上しようと思います」
ビジネスプランに関する勉強会に参加した、人事部のBさんです。参加者のビジネスプラン発表を聞いていて、ふとギモンを覚えます。「それって、出向じゃなくて人材派遣にあたらない?」
出向とは、第三者の会社に出向元の人事異動により派遣されて第三者(出向先)のために働くものですが、見た目としては労働者派遣(人材派遣)と似ています。
ですが、出向と労働者派遣とは根本的に違うもの。
そこで今回は、出向が「業」として行われる場合、労働者派遣に該当するのかどうか、詳しく確認していきたいと思います。
人事異動や雇用調整のための出向は適法

出向(在籍出向)とは、出向元企業で働く雇用関係のある社員を、出向元に在籍のまま出向先企業において、出向先の指揮命令によって出向先の仕事をさせることをいいます。
出向元と出向先の両方で二重の労働関係が成立するため、出向社員は出向元の社員であると同時に、出向先の社員でもあることになります。
これに対し労働者派遣は、派遣先との間には全く雇用関係が発生しません(派遣先の社員としての地位は持たない)。そもそも、事実上の指揮命令の関係にとどまる場合に限って「労働者派遣」と認められるものです。
出向は出向先の社員としての地位を有し、労働者派遣の場合では派遣先の社員としての地位を全く有しないという点で明白に異なります。このように法律的な差異があるとはいえ、「第三者のもとで第三者の業務に従事する」という外形的には似ています。
そもそも出向が労働者派遣にあたらないとされるのは、雇用主責任が明白で、出向社員の地位と労働条件の保障も明らかであり、それが労働者供給目的ではなく企業間の人事異動または雇用調整の方法のひとつとして、人事権に基づいて適正に行われている点にあります。
出向が「業」として行われる場合はどうなる?

では、出向と言いながらも自社で雇用する社員を営利目的で反復継続して出向させ、この出向によって企業利益を上げるという形態を継続して行う(←冒頭のビジネスプランのような場合)ケースはどうなるのでしょうか。
このような場合、通常の人事権の行使の範囲を超えて出向事業を行うという形態(営利事業としての出向)となり、職安法や派遣法で禁止されている、脱法的な労働者供給や派遣契約の形態になってしまいます。
つまり「出向を人材提供の目的で実質的な労働者派遣として行う→出向先から出向料金を受領する→労務提供料金として売上高に計上する(企業の営業活動として収益を得る)」という営利目的をもって行う出向は、人材を派遣することで利益を得ていることになるので、まさに「出向業」を行うことになり、労働者派遣に該当します。
適法な出向には該当せず、労働者派遣とみなされることになるとともに、それが無許可で行われる違法な場合には、派遣法違反や職安法が禁止する労働者供給にもあたりますから注意が必要です。
**
本文の記事に出てくる用語について、補足しておきます。
- 労働者供給とは?
自分が雇用する働き手や自分の支配下にある働き手を供給契約によって他人に使用させることをいいます。これを反復継続して供給を行うと、供給を「業」とすることになり、労働者供給の事業が成立することになります。随時他人の求めに応じて労働者を供給するには、常に働き手を自分の支配下に置いておかなければならないので、支配従属関係が存在することになります。働き手にとって職業選択の自由はなく、強制労働のおそれがあるため、職安法では労働者供給業を禁止しています。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事