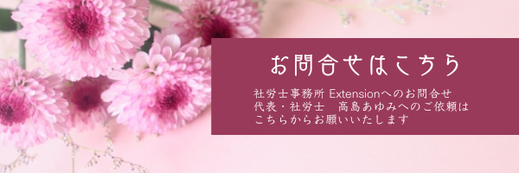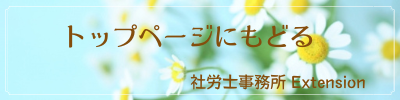採用サイトのオープン前に企業データや採用データを更新しなきゃ。そういえば、採用とは「労働契約の成立」っていうよね。・・・じゃあ、雇用契約とはどう違うんだろう?
**
採用の広報活動の解禁を前に、就職サイトの原稿を見直す人事部員のBさんです。採用フローや選考スケジュールを入念にチェックしながら「採用とはどういうことか」と考えているうちに、雇用契約と労働契約の違いについて気になったのでした。
というのも、「採用」とは社員を雇い入れることで、法律的には「労働契約の成立」とされていますが、実務において雇用契約と労働契約を意識的に区別して使い分けてはいないからです。
そこで今回は、「雇用契約」と「労働契約」の違いについて詳しく確認していきたいと思います。
雇用契約と労働契約はどう違うの?

雇用は、当事者の一方が相手方に対して働くことを約束し、相手方がその報酬を与えることを約束することによって効力を生じるものである、との旨が民法において示されています。
・・・とすると、ますます雇用契約と労働契約はどう違うの?とのギモンが湧いてきます。
この点について、民法上の雇用契約は当事者間(会社と社員)に平等な権利義務が与えられているという前提に立っています。
とはいえ実際には、交渉や情報等の面で会社のほうが優位に立っているので、平等原則が成り立っているとは言い難い状態です。そのため、労働基準法、労働契約法等の労働者保護法規による労働者保護が必要となります。
民法は契約関係全般を規定する一般法であり、労基法や労契法は社員と会社という立場にある者の間で結ばれる労働契約について定めた特別法です。そこで、「特別法は一般法に優先する」との法律上の原則によって、労働契約関係については労基法、労契法が優先して適用されることになります。
まとめると、一般的な当事者間によるものが民法の雇用契約であり、そのうちで社員と会社との間の契約が労働契約となります。
実務上はどうなる

労働契約法では、「『労働者』とは、会社に使用されて働き、賃金を支払われる者をいう」との旨が定められ、「『使用者』とは、その使用する社員に対して賃金を支払うものをいう」との旨が規定されており、労働契約の適用範囲が決められています。
そして「会社に使用されて働く」ということは、使用従属関係(一定の時間的・場所的な支配従属下において、会社の指揮命令に従い拘束されて仕事に従事するという関係)にあるとされています。
極端な例をいえば、フリーターがアルバイト募集のチラシをみて、そこに掲載されていた会社の連絡先に電話して「働きたいです」と申し込み、これに対して会社側が「いいですよ」と承諾したのなら、申し込みと承諾という合意があるので、労働契約は成立したことになります。
一般的に、実務上では雇用契約と労働契約を意識的に区分するということはありません。労基法の適用事業で社員を採用する契約が「労働契約」であって、労基法の適用のない家事使用人(お手伝いさん)や同居の親族のみを使用する事業における採用等が「雇用契約」と考えても問題はありません。
**
本文の補足ですが、労働契約の締結に際して労基法では、労働者保護のため書面による労働条件の明示義務を会社に課しています。
ですが、これは労働条件の成立要件ではなく、合意のみによって成立します(労働条件の明示、書面にすることも成立要件ではないということ)。
念のため、ご確認のほどお願いします(^o^)/


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事