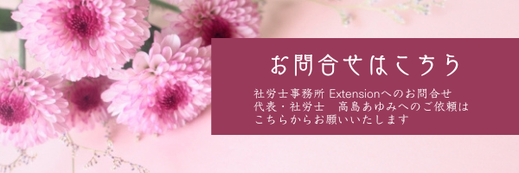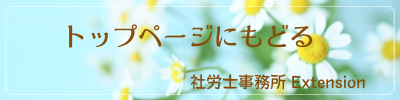「給与計算は大変なのに、他部署の人からみると”誰にでもできるルーティンワーク”と思われがちで割に合わない作業だわ~(;´∀`)」
↑人事担当者のココロの叫びです。
給与計算をはじめとする賃金実務は、決して単純作業ではなく、効率性と丁寧さが必要で、工夫のしがいがあるクリエイティブな仕事です。
会社のコスト面にも大きく関わるため、給与から控除される税金や保険料の知識が必要なだけでなく、自社の賃金体系をしっかり把握しておかなければならないからです。
そこで今回は、賃金実務のあるあるギモンについて詳しく確認していきたいと思います。
- たとえば「19時03分」とタイムカードの打刻があれば、本当に1分単位で残業の計算をしないといけないですか?
- 給与の振込先金融機関を会社が指定するのはダメですか?
1分単位で残業計算しないといけない?

「うちの会社では30分単位で残業計算をやっています。本当は1分単位で計算しないといけないのですよね?そうすると、10進法⇔60進法の変換や、端数処理でミスが頻発しそうです・・・」
残業時間の取扱いは、実務の現場で担当者悩ますトピックでしょう。
結論からお伝えすると、原則として1分単位で計算する必要がありますが、残業時間の計算については簡便化の措置が認められています。以下から詳しくみていきましょう。
5分や10分の残業時間でも、実際に働いた時間を端数として切り捨てることは、労働の対価が支払われないことになってしまいます。これは労基法違反となって認められません。
よって原則として、残業時間(法定労働時間を超える労働)に対しては、たとえ1分でも残業代(割増賃金)を支払わなければなりません。1回の残業ごとに分単位の集計を行うことになります。
残業時間計算の簡便化の措置は、あくまで事務処理の便宜上、端数処理の例外として認められるものです。端数処理の方法は通達で決められていて、次のようになります。
- 1ヵ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
- 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
- 1ヵ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、②と同様に処理すること
(昭和63年3月14日基初150号)
上記の処理は、労基法違反として扱われません。この処理でポイントとなるのが、「1ヵ月分まとめて端数処理を行う」ということです。
たとえば残業時間を毎日30分単位で切り捨てて1ヵ月分の計算を行っている場合、上記①の端数処理に反し、労基法違反となってしまいます。1日ごとに端数の切り捨てを行っていると、1ヵ月トータルでみるとかなりの誤差が発生することになるからです。
これはよくある間違いですので、いちど自社での処理方法を確認してみてくださいね。
給与の振込先金融機関を会社が指定していいか?

社員に給与を支払うとき、会社には「通貨でかつ全額を支払う」義務があります(通貨払いの原則、全額払いの原則といいます)。
そのためかつては、現金の入った給与袋を社長自ら社員にねぎらいの言葉とともに手渡す・・・といった光景がどこの会社でも見受けられたのでしょうが、現在では簡易で安全な銀行振込による方法がとられることがほとんどだと思います。
そこで、次の要件のもと金融機関の口座への賃金の支払いが例外的に認められています。
- 労働者の同意を得ること
- 労働者が指定する銀行その他の金融機関の本人名義の預貯金口座に振り込むこと
よって、毎月の給与の振込先(金融機関)の指定は、あくまで社員が行うことになります。
とはいえ、事務処理の効率化を考えると、ある程度振込先の金融機関が統一されているほうが、担当者の手をさほど煩わせることなく、ミスの防止につながるのも確かです。
なお、ここでの社員の同意については、社員の意思に基づくものであれば、その形式は問わない(口頭でもよい)とされています。社員に振込先を聞く際には書面によることが多いでしょうから、そこへ社員が振込先を記入したことをもって社員の同意を得たとするケースが実際には多いと思います。ですから実務上の対応として、社員に振込先を聞く書面に次のような提案を記載するのもひとつの方法でしょう。
賃金実務にきちんと対応するには、このように一定の知識が必要になります。その分プレッシャーもあるかもしれませんが、会社全体の仕組みを見直す機会を得ることができます。
たとえば、職場での時間外労働や休日出勤の状況にアンテナを張ることで、労働時間マネジメントがうまく機能しているかどうかがわかります。
勤怠チェックの際に、社員それぞれのタイムカードの打刻の状況をみて、「あれっ、普段と違う?」と違和感をもつことも大切です。

長時間労働が恒常的になっていないか、仕事のボリュームや進め方、本人の健康状態など、社員一人ひとりのコンディションに気付くことができると理想的です。
たしかにコツコツ粘り強さが求められる地味な面もあるかもしれませんが、賃金実務の重要性を前向きにとらえて、社員のチカラを伸ばす職場の仕組みづくりを考えていきたいですね。

■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事